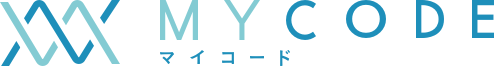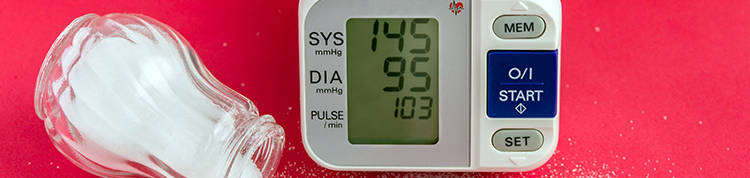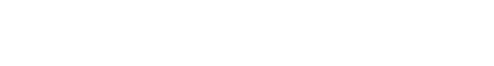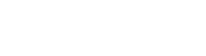- 大腸がん
- カルシウム
- 前立腺がん
- 管理栄養士

【管理栄養士コラム】あまり知られていない大腸がんの予防と “カルシウム” との関係

カルシウムや、カルシウムを多く含む牛乳の摂取が、大腸がんの予防に関連していることは、日本ではあまり知られていないようです。
世界中の疫学研究をまとめた、がん予防に関する報告書では、カルシウムや牛乳の大腸がん予防効果は「ほぼ確実」とされています(※1)。一方で、前立腺がんにおいては、これらを過剰に摂取すると、発症を促進するかもしれないといわれています(※1,2)。
今回は、大腸がんの予防にカルシウムや乳製品がどのように影響しているのかをお伝えした後、前立腺がんの予防も視野にいれたカルシウムや乳製品のとり方をお伝えしたいと思います。
1.カルシウム摂取量と大腸がん発症リスクの関係
国立がん研究センターによる研究では、約8万人の食事傾向と、大腸がんの発症について10年以上に渡り追跡調査をしています。その結果、男性において、カルシウムの摂取量が最も少ない(300mg未満)グループに比べ、最も多いグループ(700mg以上)は、40%程度もリスクが低いことがわかりました(図1)。また、カルシウムの摂取量が多い人は、乳製品の摂取量も多いことが報告されています(※3)。
では、リスクが低かったグループのカルシウム摂取量700mgをどのように考えれば良いのでしょうか。健康を維持するために摂取したいカルシウムの推奨量は、男性ですと15~29歳800mg,30~49歳650mg,50歳以降700mgです(※4)。大腸がん以外の病気予防(骨密度や循環器疾患)の観点からも、700mg程度を目指したいところです。
ちなみに、女性では、カルシウム摂取量と大腸がん発症との関連がみられなかったとされています。男性のみに関連があった理由として、女性はカルシウム摂取量が全体的に高めだったのに対し、男性は300mg以下と極端に低い人が多かったことが原因ではないかと考えられています(※3)。

図1. カルシウム摂取量と大腸がん発症リスクの関係
2.なぜ、カルシウムは大腸がんの予防に関連しているの?
カルシウムが大腸がんを予防するメカニズムが、少しずつ分かってきています。カルシウムは、大腸の発がんを促進する物質 “二次胆汁酸や遊離脂肪酸” と結合する作用があります。腸内でこれらが結合することにより、毒性が低下し、大腸の粘膜に与える発がんの影響を軽減しているのではないかと考えられています(※5)。
一方で、摂取する脂肪量が多いと、発がん物質である二次胆汁酸も増加します。チーズや生クリームは、カルシウム量は豊富ですが、高脂肪でもあります。頻度高く食べる習慣のある方は、1回の食べる量を見直す、低脂肪なものを選ぶなどを検討してみましょう。
3.カルシウムや乳製品をどのように、どれぐらいとると良いのか
①カルシウム
前述したように、大腸がん及び様々な疾患を予防する上で、カルシウム摂取量700mgは、ひとつの目安となります。国民健康・栄養調査(平成29年)によると、カルシウムの摂取状況は、20~50歳代の平均摂取量400mg台、60歳以上500mg台と、多くの方が不足傾向にあります(※6)。
普段カルシウムを意識されていない方は特に、表1を参考に、現在の食事を振り返ってみましょう。そして、不足を感じる方は、多く含む食品を追加するか、置き換えるなどを検討してみましょう。
すでにMYCODEを受けていただいている方は、アンケートにお答えいただくことであなたのカルシウム摂取量の概算を知ることができます。
なお、前立腺がんの場合、診療ガイドライン(2016年版)にて、カルシウム摂取と発症リスクの関連は未だ明確ではないとされていますが、1日に2000mg以上摂取すると、500mg未満の人と比べて、発症リスクが5倍近くなるという報告もあります(※2)。カルシウム2000mgとは、食事のみではとることができないほどの量です。カルシウムを強化した健康補助食品やサプリメントをとられている方は、その商品のカルシウム含有量を確認するようにしましょう。
表1.カルシウムを多く含む食品

②牛乳・乳製品
カルシウムをとるために、手軽に食べられる乳製品が一般的に推奨されがちです。また、乳製品に含まれるカルシウムは、体内への吸収率が高いことも良く知られています。では、この乳製品をどれくらいとると良いのでしょうか。海外の研究では、牛乳を1日200g飲むと大腸がんの発症リスクが0.91倍、その他の乳製品含めて400g/日とると0.83倍に低下したと報告されています(※7)。カルシウムを多く含む乳製品の摂取は、大腸がんの予防に関係していることは確実のようです。
一方で、乳製品に多く含まれる “飽和脂肪酸” の存在も注目されており、この飽和脂肪酸が前立腺がんの発症リスクを上げているのではないかと考えられています。日本人を対象とした研究では、乳製品を多くとっているグループ(339.8g程度)は、ほとんどとっていないグループに比べると、リスクが1.63倍だったとされています(※8)。
カルシウムを多く含む乳製品は、大腸がんや前立腺がんの予防の観点から、また、骨密度や高血圧など循環器系疾患の予防にも推奨されているため、以下2点を参考にされてください。
①乳製品をとる習慣として、特に成人男性は200g/日程度(牛乳1杯分、ヨーグルトカップ2個分)が目安となりそう。
②乳製品に含まれる飽和脂肪酸を減らす工夫として、低脂肪な商品を選ぶのもひとつ。
※目安となる700mgを目指すためには、大豆、豆腐製品・緑色野菜の摂取頻度に注目することが重要です!
今回のように、栄養素であるカルシウムや乳製品などの食品は、とり過ぎると悪影響になることもありますが、“適量”は、病気の予防に推奨されているものが多くあります。この適量は、男女差、年齢、個体差などによっても異なります。今回は、大腸がんの予防とカルシウム(乳製品)をテーマとしましたので、これを機に、ご自身のカルシウム摂取量やカルシウムを多く含む食品のとり方を見直してみてはいかがでしょうか。
※1. World Cancer Research Fund / American Institute for Cancer Research. Food, Nutrition, Physical Activity, and the Prevention of Cancer: a Global Perspective. Washington, DC: AICR, 2007
※2. 日本泌尿器科学会編, 前立腺癌診療ガイドライン2016年版, メディカルレビュー社
※3. Ishihara J, Dietary calcium, vitamin D, and the risk of colorectal cancer., Am J Clin Nutr
※4. 厚生労働省, 日本人の食事摂取基準2015年版の概要
※5. 木村修一, 最新栄養学〔第10班〕,建帛社
※6. 厚生労働省, 平成29年国民健康・栄養調査結果の概要
※7. Aune D, Dairy products and colorectal cancer risk: a systematic review and meta-analysis of cohort studies., Ann Oncol
※8. 国立研究開発法人国立がん研究センター予防研究グループ, 多目的コホート研究(JPHC Study)「乳製品、飽和脂肪酸、カルシウム摂取量と前立腺がんとの関連について」