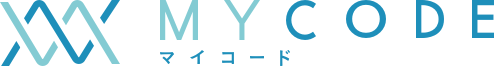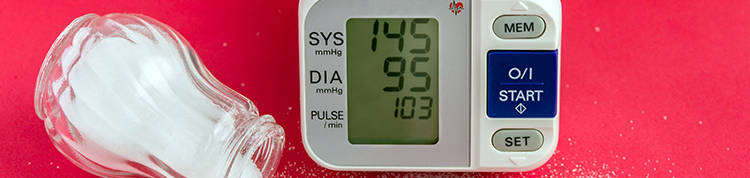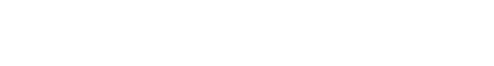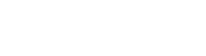- 糖尿病

【医師によるコラム】抗生物質で糖尿病が増える?
腸内細菌のバランスが良いと生活習慣病になりにくいと言われています。抗生物質は、過敏性腸症候群の改善には効果がある一方で、腸に悪影響を与えているという報告も多いそうです。

特別企画、医師の石原藤樹先生によるスペシャルコラムをお届けします!今回は「糖尿病と抗生物質の関連」について書いていただきました。
肥満や糖尿病に影響を与える腸内細菌
こんにちは。北品川藤クリニックの石原です。
腸内細菌、つまり大腸にいる細菌(ばいきん)のバランスが良いと、肥満や糖尿病などの生活習慣病になりにくく、お腹の調子も良くなる、というのは、一般にも良く知られた事実です。
しかし、それではどのような生活をして、どのような物を食べれば、腸内細菌のバランスが良くなるのか、という点については、あまりはっきりしたことが分かっていません。
抗生物質の使用が腸に与える影響は?
食生活以外に、腸内細菌に影響を与えるものとして、重要だと考えられているのが、感染症とそれに対する抗生物質の使用です。
腸に侵入した細菌が、そのまま定着して「悪玉菌」となってしまうことが考えられますし、その一方で細菌を殺す薬である抗生物質を使うと、腸内細菌を構成する正常の「善玉菌」も死んでしまって、腸内細菌のバランスに影響を与える可能性があるのです。
一部の感染症が悪いのであれば、ワクチンなどで積極的に予防したり、抗生物質も積極的に使った方が良い、ということになります。実際、過敏性腸症候群という、腸のバランスが崩れることによる症状の一部は、抗生物質を使うことにより改善するという報告があります。その一方で、抗生物質を使うとその後の腸の健康に多くの悪影響がある、という報告も多いのです。
抗生物質の使用頻度と糖尿病との関連は・・・
今年のThe Journal of Clinical Endocrinology and Metabolismという医学誌に掲載された論文によると、抗生物質を別個の時期に5回以上使用すると、使用しない場合の1.5倍、糖尿病が増える、という結果が報告されています(※)。ただ、これは抗生物質を使用するような感染症があった、という意味でもあるので、本当に抗生物質が原因であるとは、言い切れない結果なのです。
今のところは、必要性が高い時に限って、抗生物質をしっかり使うのが、最善の方法と考えて良いようです。
執筆者
医師 石原藤樹先生
プロフィール:1963年東京都渋谷区生まれ。信州大学医学部医学科、大学院卒業。医学博士。研究領域はインスリン分泌、カルシウム代謝。臨床は糖尿病、内分泌、循環器を主に研修。信州大学医学部老年内科(内分泌内科)助手を経て、心療内科、小児科を研修の後、1998年より六号通り診療所所長として、地域医療全般に従事。2015年8月六号通り診療所を退職し、北品川藤クリニックを開設、院長に就任。著書に「誰も教えてくれなかったくすりの始め方・やめ方-ガイドラインと文献と臨床知に学ぶ-」(総合医学社)などがある。