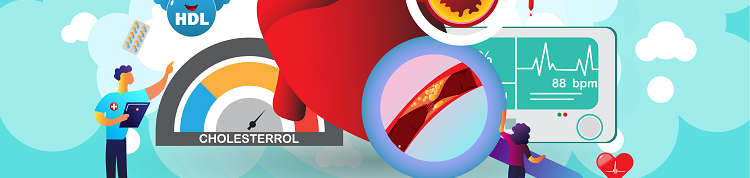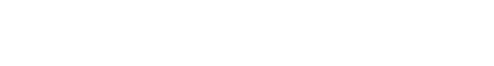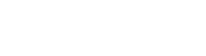子供もコロナに感染するの?変異株はどうなる?新型コロナウイルス感染症の特徴と最新報告まとめ【医師によるコラム】
新型コロナウイルス感染症(COVID-19)にはどのような特徴があるのか?
新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の世界的な流行が続いています。本記事ではこの病気の特徴と、重症化のリスク(重症化しやすい原因)をまとめています。
*本記事は、2021年6月22日時点での情報を元に執筆したものです
インフルエンザと比較した時の死亡リスクは?
新型コロナウイルス感染症の流行が始まった頃には、「新型コロナと言っても、ただの風邪じゃないか。インフルエンザと一緒だよ」というような意見が良く聞かれました。ただの風邪なのに、大騒ぎしすぎだ、と言うのです...
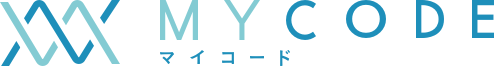

 病気・医療
病気・医療 病気・医療
病気・医療 病気・医療
病気・医療 体質・身体
体質・身体 食事・生活
食事・生活 食事・生活
食事・生活 食事・生活
食事・生活 食事・生活
食事・生活 食事・生活
食事・生活 病気・医療
病気・医療